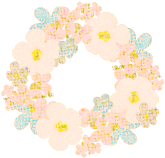かぐや姫
相馬制圧は思った程時間はかからなかった。政宗の出頭もあってか敵側の士気を大いに削ぐことができたのが要因だろう。
予定よりも1週間早く城に戻ってきたのだが、出迎えの面々の顔色がいまいち優れない。それにいるはずの者がいないことに気づき小十郎は違和感を覚えた。
そしてその違和感はすぐに判明することになる。
「綱元。もういっぺんいってみな」
上座で具足のまま座る政宗はまだ戦の中にいるかのようだった。纏う空気が全てのものを切り裂くかのように鋭い。同じように成実もいつもはあまり見せない形相で綱元を睨み付ける。恐らく自分も同じような顔をしているんだろう。
「が神隠しにあいました」
もう一度、綱元が言葉にすると庭先の岩に落雷が落ちる。落としたのはいうまでもなく。
「綱元。腹を斬る覚悟はあるんだろうな?」
「……無論」
「政宗様っ」
抜いた刀を綱元に突きつけた政宗は今にも首を斬り落としかねない空気で、慌ててそれを制した。
話を聞けば政宗達が出陣した日、使いを頼まれたはそのまま帰らず消えてしまったという。頼まれごとはこなしたらしく店の番頭がを覚えていたがそれきりだそうだ。
「…前田はどうした?」
戸を締め切り人払いをさせたのち、政宗がそう切り出した。静かに問う政宗は嵐の前の静けさと同じだ。綱元の顔からは玉のような汗が吹き出ては伝い落ちる。
今綱元の目の前に置かれているのはひと房の髪だ。先程黒脛巾組での監視を任せていた長門がそれを持って現れたのだ。その場の空気が凍ったのはいうまでもない。
「負傷し、今は床に伏せっております」
「それで何もせずただ手をこまねいていたというのか!」
「Stop.小十郎」
激昂し刀に手をかけた小十郎を政宗は手で制すると更に強くなった視線で綱元を睨み付ける。
「綱元。俺が聞きたいのはそういうことじゃねぇ」
「……」
「俺のいいたいことはわかるな?」
「……の身柄は武田の元に」
小十郎は耳を疑った。成実も同じだろう。目を見開き綱元を凝視している。今や武田は同盟国だ。しかし、この戦国の世に同盟はあってないようなもの。裏切られるとわかっていてを売ったのか?俺はそう責めるように綱元を見た。
「HA!一介の女中が同盟の証とは破格の扱いじゃねぇか」
「だけど梵。同盟の証で女中を差し出すなんて聞いたことないぜ?」
「この件についてはこれに書き記してあります」
「持ちかけてきたのは…いうまでもねぇな」
吐き捨てた政宗は差し出された手紙を読みさっさと成実に投げどかりと座り込む。小十郎の元にも手紙が回ってきたが、渡してきた成実の顔は納得できないとでかでかと書いてあった。
手紙の中身はありきたりな同盟の話との身を預かるというもの。あくまでも仮の人質で正式な手続き、人事は準備が整い次第でいいという。
「…大方、これで貸しを作ったと思っているのでしょう。あの猿め」
こんな下らないことを思い付くのは奴くらいしかいない。
「それだけじゃねぇよ。この奥州にとってがどれだけ価値があるか推し量ろうって魂胆だろうぜ」
政宗の言葉に小十郎は先日のことを思い出した。が竜の使いか否か。小十郎の中に未だ巣くうの本来の姿を武田の中にも同じように考え探っている者がいるというのか?
「んで、皆に嘘の情報を流すからにはそれなりの理由があるんだろうな?」
「…敵は身の内側にありますれば」
「Shit!」
やはり膿はなくなっていなかったのか。政宗も面倒だといわんばかりに舌打ちをした。恐らくを貶めようとしたのは政宗の奥方を後押ししている者の犯行だろう。
あの病弱な奥方が何か企てるなどありえないのは最初からわかってはいた。だが、以前候補に挙がった時に奥方の手前見逃していたのが仇となったのだろう。自分の策の甘さに舌打ちをしたくなった。
「しかし面倒なことになったな。相手が狸じゃ負かすのは一苦労だぜ?いっそ姫さんに直談判してみるか?」
「馬鹿をいうな。それこそ事が大きくなるってもんだ」
「まぁね」
「それよりその"姫"ってのはなんとかできねぇのか?相手は仮にも政宗様の奥方様だぞ」
「だって何にも知らない箱の中のお姫様だぜ?政も梵が出陣の時も姿を見せたことがない。そんな箱入りを奥方なんて俺は認めねぇよ」
「…っ」
ぼやく成実に小十郎は口を噤んだ。言い負かされた訳じゃない。内心自分もそう思っていたからだ。今し方聞いた話も世継ぎのことも本来は家を守る妻の役目だ。自分の部下を従わせることができずして何が奥方かと。
「成、あいつはあいつなりに尽くしてくれている。お前が見えないとこでな」
「……いっそ、が正室なら良かったんだ」
そしたら梵の苦労だって少しは減ったのに。成実の言葉は最もだと思うが政宗の気持ちもまた小十郎の胸に突き刺さった。
「それよりは今どういう扱いなわけ?いきなり武田へ移れと言われたんだろ?泣いたりしたんじゃない?」
「大方、物見遊山に来いとかいわれて猿飛についてったのかもな」
の名に自然と政宗の表情が和らぐ。真意を見抜けず、誑かされついていったのは後見人としてかなり不安があるが今回ばかりはそれでも構わないと思った。だが、残された髪を見る限り嫌な予感しかしない。
「猿飛という忍がいうにはを客人として丁重に持て成す、とのことです」
半ば予想通りの答えに息を吐いたが次の綱元の言葉に閉口することになる。
「それから、政宗様にはから言伝が」
「何だ?心配しなくていいとかそんな話か?」
「いえ…は"月に帰った"と思っていただきたいと」
まるで先を予言するかのような言伝に、小十郎は息を飲んだ。
-----------------------------
2011.09.30
英語は残念使用です。ご了承ください。
TOP