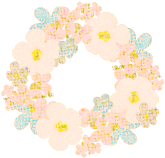気づかなくていい
最近城内が騒がしい。厨から出てきた佐助は行きかう武将達を横目で見ながらお椀とお茶が乗った盆を片手にひょいひょいと廊下を歩いていた。
「この辺かな」
そういって辺りを見回し、誰もいないことを確認すると中庭に出て屋根に飛び乗った。足音を立てず屋根伝いに歩いていくと屋根と屋根の継ぎ目近くにこんもりとした人影が見える。
まだまだ残暑が厳しいっていうのに黒い羽織を頭から被ったその人物を眺めながら佐助は「暑くないのかね〜」とぼやいた。
「ちゃん。いわれたもの作ってきたよー」
「!佐助さん…っ」
こんな屋根に忍以外こないだろうに、は思いきり肩を揺らし振り返った。そして佐助の顔を見た途端一瞬だけ泣きそうになり、それからふにゃりと困ったように笑う。
今上田城ではどうやってと幸村を添い遂げさせるか城内外問わず躍起になっている。
それはというのも、どこから漏れ出たのか奥州の争いごとが片付き次第が帰ってしまうと広まってしまったせいだ。それを聞いたは始めこそ笑っていたが最近はすぐ帰るかいっそ別の国に行きたいとぼやき始めたくらい上田の面々は煩くてかなわない。
朝起きて女中のひと言に始まり夜は遅くまで懇々と家老に説得されている。昼間は昼間で外に行けば幸村を慕う民に声をかけられ、追いかけられ、ついには屋根の上に逃げ込んでしまった。
まあ、ちゃんじゃなくてもあんな必死な形相で追いかけられたら逃げたくもなるけどね。
「誰にも見つかってない?」
「見つかってないよ。俺様を誰だと思ってるの?」
「佐助さま」
疲れきった顔で皮肉るに佐助はいつもの自分を仕舞うと、向かい合うように座った。を膝の間に座らせ佐助は椀の中にあるものを指で掬うと彼女の口先に持ってくる。
「ほら、あーんして」
「あー…、ん」
糸を引く半透明のものをは口を開けて指ごとくわえた。因みにこれは水飴である。砂糖の代わりによく使用するのだがそれをまさかが食べたいというとは思いもよらなかった。
確かに以前甘いものは疲れに効く、と豪語していたがそれを実践するほど疲れているとは。
他人を癒すことが出来る力は大分制御が出来てきたものの、肝心の自分を癒すことはできないものだった。だからこうやって甘いものを摂取しなければにとっては割に合わない状況なのだが、佐助にしてみれば棚から牡丹餅ともいえる。
口に含むと口内に甘みが広がったのかの頬が緩む。それを小さく笑った佐助は指を引き抜いてまた椀の中から水飴を掬うとの唇に押し当てた。
「んーちょっと待って。垂れる垂れる…ていうか、箸とか棒とかなかったの?」
「あーそれは失念してたねー」
勿論確信犯である。
別にいいんじゃない?と気軽にいってみるとは眉間に皺を寄せて少し考えたが「佐助さんが気にひないならいいへど」と指を口に含んだまま零した。それだけで十分卑猥なんだけどね。
俺の手首を掴んだは水飴を舐め取ろうと必死に舌を動かす。一気に2本を口に含むのは大変なようで、1本ずつ丹念に舐め取る姿に佐助は笑顔を貼り付けたまま内心如何わしいことをしてる気分でいっぱいになっていた。いわば理性との戦いである。
ちろちろと動く赤い舌がいやらしいし、分厚い手の皮じゃあまり感覚もないけど歯が当たったり、爪の辺りを舌が通る度背中が粟立つ感覚が走る。
ちゅっと吸われる度に理性へのダメージが追加されてる気分になり佐助は短く息を吐く。そうさせたのは自分だけど。あー生殺し再びだわこれ。
「ちゃんってば、そんな舐め方どこで覚えてきたの」
「?どこって…習うものなんです、か…」
軽口のつもりで質問をすれば、指を口から外し首を傾げたが途端に顔を赤く染めた。あ、この子わかってる。
すかさず「うわーやーらしー」と笑ってやると、更に顔を赤く染めて「ちっ違!」と否定してくる。ニマニマと笑みを浮かべていれば赤い顔のまま怒って椀を奪おうとしてきた。それをすんででかわした佐助は水飴に浸した指を小さな口の中に滑り込ませた。
「んー!んー!」
「あはー何いってるか俺様わかんなーい」
「んーっ!!」
小さな舌を指で弄ぶとと抗議の歯が佐助の指を挟む。嫌がるならもっと強く噛めばいいのに、それ以上はしてこない小さな歯にいいようのない気持ちになる。
さすがにこれ以上はちょっとまずいかな。悪戯してるのは楽しいんだけど見てると食べたくなる。少し残念に思ってる自分に苦笑しながらついっとの上顎を撫で上げ指を引き抜いた。
「…佐助さん。前より性格悪くなってません?」
銀色の糸が指との唇を繋ぐように伝う。それが異様に卑猥でぞくりとした。それに目元を赤く潤ませたが上目遣いに睨んでくるから余計に心臓に悪い。
赤く熟れたような唇を凝視する目を無理矢理引きはがした佐助は水飴がべったりついている指をおもむろに口に含んだ。すると目の前から「にょわーっ!」と変な声が聞こえ、を見れば真っ赤な顔で鯉のように口をパクパクと動かし固まっている。
あはーそうだよねー。さっきまで自分が食べてた指だもんねー。紛らわしの為とはいえちょっと考えなしだったかも。
「だってもういらないんでしょ?」
「…っか、勝手にしてください…」
真っ赤に茹で上がった顔では頭を抱えると「いや、別にいいんだけどね。いいんだけどさ…こう、心の準備というものが」とブツブツ呟いている。そういう反応されると加虐心がくすぐられるんだけどなー。
わかってないね、との反応を見るように音を立てて指を舐めると「ええい!やめんか!!」とどこかの武将のような口調で指を引き抜かれた。
今にも「破廉恥でござるー!」と自分の上司みたいに走って逃げたそうな顔のは、懐紙を引っ張り出すと俺の指を乱暴に拭う。慌てちゃって、可愛いねぇ。
「ちゃん、顔真っ赤」
「だ、誰のせいだと…っもう本当、心臓に悪い…私疲れてるのに…」
「ごめんねー俺様ってこういう性格だからさー」
「そんな苛めるの好きですか!慌てふためくのを見て楽しんでるんですか!」
「だってちゃん可愛いから」
好きな子ほど苛めたいっていうでしょ?この軽口もには届かない。わかってて投げている。にっこり微笑んだ佐助にはガクリと肩を落とすと「子供ですか…」と嘆息と一緒に吐き出した。そんな顔も可愛いとか思ってる俺は相当な阿呆だ。
張り合っても負けは見えてるのに。それでも付け入る隙はないかって探っている。それこそ仕事冥利につきる考え方だ。
「まー機嫌直してよ。俺様が暇な時はこうやって身を隠してあげたり甘いもの作ってあげたりするからさ」
「そこだけは信用してます」
は佐助の胸に寄りかかるように頭を置くとハァ、という溜息と一緒に目を閉じた。それだけで心も身体も熱くさせるのだとこの子はいつか気づいてくれるだろうか。
-----------------------------
2011.11.27
実は決壊間近だったり。
TOP