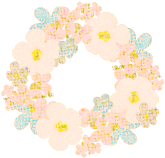息も出来ない
使い終えた食器を片したがあることに気がついて外の井戸まで来ていた。冬の夜は一段と凍えてぶるりと身体が震える。ハァ、と何度も手を温めながら井戸の水を汲み上げるために綱を引っ張るが、重みのせいかいつもより綱が掌に食い込む気がする。
「こぉら。こんなとこで何してんの」
「あ、佐助さん。おかえりなさい」
後ろから包むような温かさに肩を揺らしたは思わず持っていた綱を手放してしまった。あ、と思ったときはカラカラカラ、と滑車が回ってしまったが落ちきる前に後ろにいた佐助が止めてくれた。
ビックリした、と振り返れば「怪我人が何してるの」と呆れた顔が部屋から漏れる明かりで見てとれる。
「カメに水を溜めておこうと思って」
「そういうことはここの下女に任せておけばいいでしょ」
「でも、気づいた時にやっておかないと…」
明日になって足りない!とかになって水汲みしても凍ってたら洒落にならないし。
その発言に佐助はまた溜息を吐いたが、今度は咎めず「俺様がやってあげるから」と綱を引っ張った。
「ありがとうございます、佐助さん」
「まったく、ちゃんは自分が怪我人ってこと忘れてるでしょ?」
「忘れてませんよ」
「背中痛いくせに」
「このくらい平気です」
綱を引っ張る時、背中が少し引きつる感じがしたのを佐助は見逃さなかったらしい。相変わらず目敏い。それを勘ぐられたくなくてわざと強がれば「馬鹿いわないの」と小突かれた。
「佐助さんこそ幸村さまに報告しなくていいの?」
「これをカメに入れたら行って来るよ。ちなみにあと何回汲めばいいの?」
「そうですね。あと3回くらいかな」
「じゃあ先に報告した方が早いか。…俺様が戻ってくるまで家の中にいること。いいね?」
「でも、佐助さんも疲れ」
「いいね?」
そんなに凄まなくてもいいじゃないですか。有無を言わさない笑顔に怯んだは渋々頷くと佐助はホッとした顔で「よろしい」と頭を撫でた。
*
「温泉にはもう浸かった?」
これでおしまい、と報告を終えた佐助を律儀に待って水汲みを眺めていた(だって手伝わせてくれなかったんだもん)に佐助がこっちを向いて首を傾げた。
その問いに頷くと佐助はにっこり笑ってが座ってる隣に座り込む。
「佐助さんは…まだですよね」
「そうそう。まったく忍使いが荒いんだから…まあ、こっそり隙を見て入るつもりだけど」
「是非そうしてください。頑張った佐助さんが入れないのはおかしいですもん」
「そういってくれるのはちゃんだけだよ…」
「?そうですか?幸村さまもそう思ってるんじゃないですか?」
「あー…いつもなら、ね。でも今回は忘れっぽいかも」
涙ぐんだり遠くを見たり今夜の佐助もお疲れのようだ。
そんな彼を眺めていると「そうだ」と機嫌よく手を広げてくる。可愛いなぁ、と思わず微笑んだが、つられて手を伸ばしたところで留まった。
「?どうしたの?」と待ちわびてる両手にの手もフラフラしてしまう。
「あーうん。その、なんというか」
脳裏に不機嫌な政宗が浮かんで消える。うーん、下心はないんだけどなんか罪悪感があるかも…。政宗にいわれたばっかだしな…。
佐助と自分の手を交互に見てどうしたものかと考えていると、ばふっと何かが覆いかぶさった。
「うおっぷ!佐助さん?」
「そんな顔しないでよ。ちゃん」
ひんやりした着物の感触と一緒に佐助はを抱え上げると、自分の膝に乗せ、もっと密着してくる。ぴったりとくっつく頬の感触にいつの間に額当て取ったんだ?と目を瞬かせた。
「佐助さん頬も冷たいですよ。熱いお茶か、確か鍋汁が少し残ってたんで温めますよ?」
「うん。じゃあ熱いお茶貰おうかな」
「はい…って、佐助さん?」
放してくれないと用意できませんよ。そういって彼の肩を叩くが佐助は何故か笑って放さない。
「もう少しこのままがいいかも」
「…お疲れですか?」
「うん。ちゃん不足」
「一昨日ぶりじゃないですか」
「俺様って疲れやすいの」
「え、具合でも悪いんですか?」
もしかして豊臣戦の時にどこか怪我でもしたんだろうか。
佐助は怪我をしても隠していわないままにしてそうだ。
そう思ったら急に心配になって届くだけ佐助の背中とか擦ると「くすぐったいよ」と頬を擦り寄せてくる。甘えてくる猫みたいだ。猫にしては大きすぎるけど。
「佐助さん、重くないんですか?」
「このくらいの軽さで重いとかいったら忍失格でしょうよ。あーでも前より大きくなったかな?」
「…それは遠まわしに太ったと…? 」
「あはは。怒んないでよ。甲斐に戻ってきた時のことを考えたらいい傾向なんだから」
「……」
「それに、抱き心地も良くなったしね」
「…やっぱり太ったって意味じゃ… って、佐助さん?く、首はやめてくださぃ…!」
「…もしかして竜の旦那に何かいわれた?」
「っ…え?!いえ、何も?」
しまった。声が裏返った。
「ふーん…」
「!いやいやあの、佐助さん?!わはっ」
「俺様に近づくなっていわれた?」
「ひゃははっやめっ耳もダメ!息吹きかけないでっ…あははっ」
「こういう風に触ったりしちゃダメっていわれた?」
「う、ひゃあっ佐助さん、ちょ、触り方がなんか…」
「竜の旦那が好きだからこういうことはもうしたくないとか?」
くすぐったいんだけど何か手つきが変にやらしくて、首も息と一緒に柔らかいものが当たってじわじわ落ち着かない。時折、「ちゅ」と音がするから尚更だ。
逃げようと身を捩ってみたが笑って引き戻された。
佐助の手がの頬を捉えて視線を合わせてくる。絡まった視線に自ずと顔が熱くなった。
「ちゃん顔真っ赤」
「いや、これは佐助さんが変なこといったり触ったりしてくるからで」
「変な気分になっちゃった?」
「あのですね!そういう冗談は嫌いです」
「そんなに竜の旦那のこと好き?」
「なっ話をすりかえないでください!」
「旦那のご正室の一派がちゃんの命をまだ狙ってるのに?」
それでも竜の旦那のとこに帰りたい?佐助の言葉にギクリとした。
そういえばそんな話もあった気がする。随分昔の話に思えるけど…。ああでもそうだよね。政宗には正妻がいるんだ。傷が治っても奥州には帰れない。帰っても居場所があっても納得できるのかあまり自信がない。
「…私を苛めて楽しいですか?」
「そんなつもりはないけど…でも、奥州には帰ってほしくないなあって思っててさ」
「へ?」
「正直、ちゃんが持ってる能力は魅力的だと思う。それこそ噂が広まれば誰かしらに狙われるんだろうなってわかるくらいにはね。でもそれだけじゃない…。俺はさ、」
「?」
「ちゃんのこと、その辺の子供とは違うってもうわかってる。危機感足りないのも、考え方も、知識も、内側に入れた人間を懐柔してしまう甘さも今まで見てきたどこの誰とも違う…最後は多分俺くらいしかわからないだろうけど、」
「……」
「……なぁ、、」
佐助の指先がの頬を辿る。ただそれだけなのに性感帯をなぞられたような錯覚に陥った。ぶるりと背中が粟立つ。
「本当は、大人同士の癒し方も知ってるんだろ?」
顎を捕らえた親指が唇をなぞる。そして佐助の目が誘惑するように細められぶわっと身体から火が出そうになった。う、わ。何これ。息ができない。頭がチカチカする。
「奥州に帰らないっていってよ」
そしたら俺もちゃんとちゃんを"大人"として迎えるから。
-----------------------------
2011.09.23
TOP