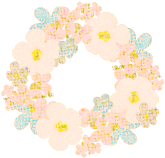泣いてはいけない
ここ数日、政宗の機嫌が悪い。何かした覚えはないから自分じゃないと思いたいが城よりは狭い屋敷とそれなりに近い部屋と顔を見る回数に緊張は高まるばかりだ。
昨日は1日中雪が降って温泉に浸かれなかったし、湯治ということで仕事も出来ないからは暇で暇でどうしようもなかった。
そんな訳で今は薪を割っている幸村を眺めているんだけど。
「殿。寒くはないか?もし寒いようなら中に入っていても良いのだぞ」
「ううん。大丈夫です」
今日は昨日と打って変わって晴れたからより一段と幸村の笑顔が眩しい。汗を拭う彼にやっぱ大きなワンコだよなぁ、と思った。こんな寒い冬場でそんなに元気なんだもん。
「幸村さま見てると元気になるし」
「そ、そうでござるか?!」
脳内で雪原を走り回るワンコを思い浮かべながら微笑むと幸村は顔を赤くして「殿!」と迫ってきた。
「その、殿。このまま甲斐に留まってはくださらぬか?甲斐は過ごしやすい所故、怪我の治りも良いと思うのだが」
「幸村さま。お気持ちは嬉しいのですが」
幸村がいってるのは春以降のことも含めたものだろう。雪が溶けて春の桜が咲く頃に下山して政宗と馬勝負をする。そんな約束までこぎつけたがそれ以降は不透明だ。
自分は伊達家の下女だし後見人は小十郎だからずっと甲斐にいることはできない。政宗が帰るといったら私も帰るしかないのだ。
こんなにお世話になってるのだから情が移らない訳ないけど、こればっかりはどうしようもない。
折角できた友達だけど、と見上げれば真剣な目で見てくる幸村がいて。不覚にもドキリとした。
「某、幾度となく進言仕ったが、再度いおう。某は…いや俺は殿とめ」
「はーい。そこまでねぇー」
まるでデジャヴのような光景には目を瞬かせる。引き離された向こうでは幸村が迷彩服を着る彼に文句をいっていた。その後姿に無意識に手を握り締める。
「佐助、1度ならず2度までも!どういうつもりか!!」
「旦那〜。俺様、旦那のこと救ってあげたんだよ?」
「?何の話だ!」
「旦那、その話になると必ず舌噛むじゃない。前にみたいに思い切り噛んで、食後ににっがーい薬飲みたくないでしょ?」
「うっ…」
そうだったんだ。確かに血は出てたからな、と小さく笑うと佐助が振り返りギクリと肩が揺れた。
「それから、ちゃんは病人なんだから身体冷やすんじゃないの!」
「ご、ごめんなさい」
久しぶりのオカン降臨。「何かいった?」と黒い笑顔の佐助に勢いよく首を横に振ると中に入るように即された。
*
巻き割りが途中ということで1人取り残されることになった幸村は、置いていくなとを見つめていたがあえなく佐助に戸を閉められてしまった。
戸の向こうで文句を言う上司に聞く耳も持たないのか直属の忍びはさっさと歩いて行ってしまうからここの主従関係は相変わらずあべこべである。
もで佐助にこれ以上怒られたくなかったのでそのまま彼についていったがしばらくして足を止めた。佐助はの前をヒタヒタと音もなく歩いていく。そんな彼をは声に出して呼び止めた。
「佐助さん、」
廊下は外よりは暖かいけど息はほんのり白い。生活音も殆ど聞こえないような静けさの中、ゆっくりとした動きで佐助が振り返る。部屋の間にある廊下は光を遮って薄暗い。
それでも夜よりはマシで佐助の表情を伺うことはできた。
「心配してくれてありがとうございます。でも前よりは大分いいから。幸村さまのこと怒らないでくださいね」
「怒らないよ。呆れてるだけ」
佐助は溜息と一緒にそう呟くと身体をこちらに向け手を伸ばす。籠手をつけてない手はの頬に触れようとしたがその瞬間肩が揺れてしまった。「あ、」とバツの悪い声を漏らすも佐助は気にせずの頬に触れ親指で撫でてくる。
「真田の旦那と一緒にいるってだけで、今度こそ言われるんじゃないかって焦った俺様に呆れてるだけ」
「そしたら丁重にお断りするつもりですよ」
秋の紅葉に幸村に告白紛いをされたことはまだ覚えてる。周りに乗せられて、ていうのがかなり有力な流れだろうけど幸村が公言してしまえば後には引けなくなる。それによって何かが変わるし、動かされる人間も多い。
それでも自分にとって政宗への気持ちは揺るぎない部分だから断るのだろうけど。
の視線に佐助はもう一度溜息を吐くと「そう、」と手を放し背を向けた。
「佐助さん」
「……何?」
立ち止まった背中に少し言葉が戸惑われては息を吸う。冷えた空気に鼻がツン、と痛くなった。
「私、政宗さまのことが好きです」
「うん。知ってる」
「だから、幸村さまがいっても信玄さまがいっても奥州に帰ると思う」
「うん」
「佐助さんの気持ちには応えられないの」
傲慢で、もし佐助が冗談で言ってたら目も当たられないような言葉だけど、彼は茶化すこともなく「そう。わかった」とだけ答え、その場を後にした。
数分か数十分かわからない間立ち尽くしたはほう、と嘆息を吐くとズルズルと襖にもたれかかりそのまま床に座り込んだ。これでよかったのかどうかはよくわからない。言葉も政宗への気持ちも嘘はないけど佐助を傷つけるのは本意じゃないのだ。
「こういうの、しんどいなぁ」
仲良くしてもらってただけに罪悪感は拭えない。育んだ友情ももう壊れてしまったのかもしれない。そう思うと辛くて悲しくて涙が滲んでは強く、強く、唇を噛みしめた。
-----------------------------
2013.12.25
TOP