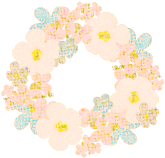僕の可愛い妹・2
決勝は誰が予想しただろう。真田隊きっての主従、幸村と佐助の対決になった。部下達はてっきり佐助が棄権して幸村の不戦勝になるのだと思っていたのだが土俵には真剣そのもので睨みあう主従がいる。
「旦那。手加減はしなくていいよね?」
「ああ。どこからでもかかって来い!」
幸村は大きく深呼吸をし、裸足でにじり寄る。佐助も同じように足指を使って前へと進んでくる。
とても静かだった。誰もが固唾を飲みこの試合を見つめている。
先に動き出したのは佐助の方だった。
いつもならば相手が動くまで待つ主義の男が焦っているのだろうか。そう思ったが膝に伸ばしてきた手に幸村は慌てて身を翻し逃げた。そしてそのままつっこむのかと思われた佐助も縄尻に足を引っ掛け踏み止まる。
持久戦は不利とわかっているんだろう。忍としては群を抜いている佐助だがそれを維持する為に削ったものがある。それがこの試合では必要なことだ。
そう思い踏み込めば、素早い佐助の方が1歩早く幸村の腰紐に両手をかける。幸村も辛うじて片手を佐助の腰紐に縫い付けた。
「佐助。よもやここでお前の本気が見れるとは思ってなかったぞ」
「時間を引き伸ばそうったってそうはいかないよ?」
「そんなに"いつもしていること"が誰かにされるのは嫌か?」
ほんの一瞬、怯んだ佐助を見逃さず幸村は掴んでいた片手に力を込めると思い切り土俵際まで近づいた。
「うわっらしくないことしないでよ!ビックリするじゃない!ていうか旦那こそ何躍起になってんの?」
「俺が躍起になるのはいつものことだが?」
「……うわー…旦那が性格悪くなってるー…」
熱くなった俺を窘めるのはいつもお前じゃないか。そう思ってムッとすれば佐助が引きつった顔で笑うのでそのまま腕に力を入れて押し出そうとする。しかし、佐助も足に力を入れていてなかなか倒れない。
「いいよ。旦那がそういうことするなら俺にも考えがある」
段々と腕が痺れてきた。だがここで力を抜けば負けは必死。負けるという言葉が嫌いな幸村は更に力を込めて佐助を追い出しにかかるが相手はニヤリと笑って俺を見てくる。
「ちゃんがつけてるあの髪紐、竜の旦那からの贈り物だってよ」
「…っ!」
「寝る時も肌身離さずつけてるんだって」
いつか帰りたいっていってたよ。そういって佐助の腕に力が入る。そのまま押し出されそうになった俺は一瞬遅れたが、ふり絞れるだけの力を込めて身体を捻りそのまま佐助を押し潰した。
「幸村さま?!佐助さん?!」
「おい!大丈夫か?!」
慌てた表情で駆けてくると慶次に幸村は身体を起こすと自分の下に佐助はいなかった。あったのは変わり身の術で使う丸太だけ。
「旦那に潰されちゃ怪我しちまうもん」
「佐助、」
「2人共大丈夫ですか?!」
膝をつくに幸村は大丈夫だと答えたが手首にある髪紐が視界の端にちらついていた。そうか、政宗殿からの貰い物なのか。
そう納得しているのになんだろう。このもやもやとした感覚は。
小さな手に握られ余っている自分の手を眺めながらぼんやりしていると「おめでとうございます」という声が聞こえてきた。
「さすがですね!幸村さま1番ですよ!」
「本当、馬鹿力持ってる旦那には敵わないよ」
「何言ってんだよ!アンタだって結構本気だったろ?」
「さあ。俺様いつ本気出したっけ?」
「…殿」
わいわいと頭上で騒ぐ佐助や慶次、それから部下達の声を聞き流しながら幸村は目の前の少女を見据えた。首を傾げさらりと零れる髪はやはり短くとも綺麗で、つい触れたくなってしまう。
「優勝をしたので褒美をいただけぬか?」
がピシリと固まった。
その目をじっと見つめていれば右往左往に彷徨わせ「別に大したことじゃないんだけどな」とか「褒美というか罰ゲームというか」とブツブツ独り言を呟いている。もう一度「殿」と呼べば背を正したが俺を見て諦めたように肩を落とした。
「怒らないでくださいね」
そういって手を伸ばすとは幸村の頭を優しく3回ほど撫でてそれから背に手を回しぎゅうっと抱きしめる。その衝撃に目を見開いた俺と一緒に周りの部下達がおおおっと声をあげた。
「今日1番に格好よかったです」
そういって背中をぽんぽんと撫でられその温かさは消えた。なんともいえない気持ちだった。
最初に感じたのは物足りなさだ。もう少し、と思ってしまった。それからじわじわと身体の中で広がる温かさにいいようのない気持ちが蔓延する。なんだろうかこの感じは。まるで陽だまりの中にいるような、もう思い出せない母親に抱きしめられたような錯覚。
ほんの一瞬しか感じれなかった柔らかい温もりにどうしたらいいのかわからず、をじっと見つめていると眉尻を下げた彼女に「大丈夫ですか?」と心配げに聞かれ、慌てて頷く。安堵するようなの微笑みにまた胸の辺りが温かくなった。
「だからいったんですよ。こんなの褒美にならないって!」
「そんなことないだろ?どうだった?感想は」
「感想?」
「これされると佐助の奴デレデレになる…ってわー!何投げてきてんだよ!!」
「前田の旦那。いっぺん死んでみる?死んでみようか?ていうか今すぐ殺してあげるよ 」
頭の上を飛び交うクナイに慶次は顔を真っ青にさせると一目散に逃げた。その後を佐助が地を這うような笑いを上げて追いかける。ああなると手がつけられないことを知ってる幸村はただ見送るしかない。
部下もそう思ったのか早々に身の安全を考え散り散りに散っていった。
あとに残されたのは幸村とだけ。
「殿」
「は、はい」
慶次達が消えていった方を心配そうに眺めていたが再びこちらに向くと、幸村は息を吸い込みもう一度"ご褒美"をお願いしたいと申し出た。
もう一度という俺に目を瞬かせていただったが、苦笑すると「わかりました」と了承して先程と同じように頭を撫で幸村を抱きしめる。その温もりに目を細めた幸村は離れようとした少女をもう少しと抱きしめ返した。
腕の中にすっぽり収まってしまう小さな身体に母親に抱きしめられたような感じ、というのは変な喩えだと思った。こんな細くて小さな身体に守ってもらうなど男子としてあってはならない。兄というからにはどんなことがあろうともこの手で守りたい。そう思った。
「あの、幸村さま…?」
「殿。殿のことは某が、この身にかえてもお守りいたしまする」
おずおずと上目遣いで伺うに、幸村は本当の妹のように慈しみを込めた笑みで微笑めば彼女の顔は途端に赤く染まった。
赤い顔のまま黙っているの綺麗な髪を梳いてやれば、肩が揺れ「あああありがとうございます」というどもった言葉が返ってきて幸村はこっそりと笑ったのだった。
その後、慶次は数週間上田城に戻らず、佐助の給料が半分に減らされたと嘆き悲しむ声が城に響いたのはまた別の話。
-----------------------------
2011.10.17
BACK //
TOP