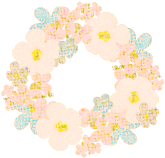それでも君を想ふ・3
水を得たのは政宗だけではなかったようだ。
「前よりも、強くなってる」
「!ごめんなさい、痛いですか?」
腕の強さかと勘違いして離れるに「そうじゃなくて、」と彼女の手を握った。自分の手の温度が確実により上がっている。さっきまで同じくらいだったのに。
深呼吸をして「もう一回」といえば不思議そうな顔をしながらももう一度繰り返してくれた。頭を撫でられるのはそれほど威力はない。
問題は抱きつかれた時だ。そう構えていたのに与えられた温かさに眩暈がした。身体の芯から温まっていくのと同時に感じる甘い匂い。違う、そうじゃないと頭を振って忘却した佐助は冷静に考えた。
温かさは、一気に身体中に広がる。例えるなら大雑把だけど温泉に浸かったような感覚に近い。身体の中に溜まる毒素を全部消化してしまったみたいに満たされている。以前はここまでの力はなかったはずだ。
「大丈夫ですか?」
「うん。問題ない。さっきは久しぶりだったから、ね」
不安そうに覗きこんでくるに佐助は笑って彼女の顔を肩に押し付けた。暗がりとはいえ今は顔を見られたくない。
間違いなく顔が赤く染まっているだろう。これは不意打ちを食らった羞恥心、と念じながら倒れないようにの腰に手を回す。決して触れられて嬉しくなったわけじゃない。
薄手の生地から伝わる体温に正直クラっとしたがこの子は子供、手を出したら嫌われる、この子は人のもの、と何度も念じて脳裏に焼きつき始めてる大人のを打ち消した。
「やっぱり強くなってるね。力」
「そうなんですか?」
「うん。これならさっきくらいでも十分進歩したと思うよ」
「本当?!」
べったりくっついた己の手を無理矢理剥がした佐助に対してするりと離れたに心底羨ましいなと呆れた。やっぱりこの子が見てる相手は自分じゃないんだなってまざまざと見せ付けられた気分だ。
そんな気持ちを表に出さないように、嬉しそうに微笑む彼女へ笑い返せばもう一度抱きつかれた。この子、俺の理性を試してるのかね。
「ありがとう佐助さん!」
「努力してるのはちゃんでしょ」
「私が頑張れるのは忙しいのに付き合ってくれてる佐助さんのお陰ですから」
可愛いこといってくれるじゃないの。掛け値なしでこんなこというんだから本当、出来た子供というか、出来すぎた子供というか。
正直、ただの子供なら夜遅くに顔を見に来たりしないし、力の制御だってある程度で線を引いてそれ以上はしてやらない。それにいつもの自分なら利用価値を計算して行動してる。負担になることは絶対にしない。
だけどが相手だとどうしても駆け引きがすっぽ抜けてしまってしまう。この体温が心地よくて仕方ないんだ。振り払いたいのに、振り払えない。こうやってなんでもない素振りをしてるのが精一杯なんて、猿飛佐助も落ちたもんだよ。
「そういえば、真田の旦那がちゃんに歌をせがんだんだって?ごめんねー」
「ううん。気に入ってもらえるとは思ってなかったけど…何回も歌わされるとも思ってなかったけど…気にはしてない」
「本当、ごめんね」
一瞬、まっすぐに行動できる幸村が羨ましいなって思ったけどを見たらそうでもないかも、と思った。やっぱり相当恥ずかしかったらしい。頭を撫でてあげたら嬉しそうに擦り寄ってきた。うん、旦那よくやった。
それにしても、ちゃんがちょっとでも俺を"そういう対象"で見てくれればなあ。こうやってこめかみに接吻してもくすぐったがるだけだし。この辺は年相応というかむしろ子供っぽいというか。でも雰囲気とか匂いは年頃の娘よりもずっと色気があって馨しいんだよね。
かといって無理矢理ってのも憚れるしなあ。独眼竜のあてつけみたいになっちゃいそうだし…それで嫌われたら立ち直れなそうだ。
もっといえば、もう少し(肉体的に)熟れてから味見したいところなんだよね。…そんなこと分析しちゃってる時点で手が出しづらいってことなんだよなあ。
やっぱりは自分の上司のように一途に政宗しか見ていないのだろうか。そうなると自分は相当不毛な戦いに挑んでいることになる。前に政宗に喧嘩を売ったことを思い出した佐助は俺も若いなぁ、と苦笑してを引き離した。
「今日は遅いからもう寝ちゃいなさい」
「はぁい。あ、佐助さん。今日はまだお仕事あるの?」
「ん?ないけど」
「そっか。…お仕事ご苦労様でした」
明日も頑張ってくださいね。と布団に潜りながら微笑むに佐助は「はいよ」と淡白に返して部屋を出て行った。しばらく冷えた廊下を歩いた佐助は、ふと立ち止まると周りを確認して嘆息と一緒にしゃがみこんだ。
「自覚ないってのも困りもんだよねぇ」
の癒しの力は佐助にしてみれば後付みたいなものだ。
自分がに欲したのはあの言葉なのだから。
敵国の、しかも忍には最初から労う言葉を寄越してきた。幸村も忍に対して破格の待遇をしてくれるが、に感じるものはそれとはまた別の話で。
初めて手に入れたいと思ったのだ。
あの声で、あの視線で自分の為だけに言葉をくれたなら、と。
混乱に乗じてここまで連れてきてしまったけど、そろそろお開きの時間が近づいているらしい。
俺も旦那のこといってる場合じゃねぇな。とカラ笑いを浮かべ立ち上がった。
顔はまだ赤い。きっと耳まで赤いんだろう。不毛な恋だとわかってるのに諦めることが出来ないのは、未だに自分を頼るの存在があるからかもしれない。
「こういうのを蛇の生殺しっていうのかねぇ」
あーあ、俺って可哀想。そうさめざめとぼやき、佐助はもう一度溜息を吐くと闇の中に消えていった。
-----------------------------
2011.11.21
BACK //
TOP