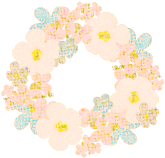初夜 ・1
ロマンチックに照らされた明かりの中、は湯から上がると身体を拭き、まっさらな夜着に着替える。いつものように適当な帯の締め方はせず、手伝ってもらいながら顔にはほんのり化粧も施された。
「。覚悟は決まりましたか?」
「……はい」
小指で唇をなぞり紅をつけた目の前には慎重な面持ちの喜多がいる。その眼差しをしっかり見据え頷いた。
心臓はさっきから飛び出そうなくらい騒がしい。
本日、私は伊達政宗さまに嫁ぐことになりました。小十郎のお城にいる侍女3人と家来が十数人を引き連れて入城し、白無垢を着て極々一部の身内だけで婚儀を挙げた。
ただ時代劇にあるような結婚式ではなくメインの2人だけで厳かに、三々九度も喜多を挟んで執り行われた。一応説明は受けたが式のギャップの差があって未だふわふわしてるところがある。お酒のせいかもしれないけど。
喜多に連れられてよく磨かれた廊下を歩いていく。この辺掃除したことあるな、なんて思いながら奥へ進んでいくと喜多が立ち止まりもそれに習った。
「Come on」
独特で一言でわかってしまう言葉には少し治まっていた心音が大きく胸を叩いた。スッと開かれた襖の向こうには明かりに照らされた政宗がいて、自分と同じ夜着に身を包みどっかりと布団に座ってこちらを見ている。
並べ敷かれた布団には緊張の息苦しさを感じるが喜多の指示で慌てて部屋へと足を踏み入れた。
電気がないこの時代は行灯をつけたところで薄暗くて勉強や針仕事には向いていないがこういう時は無駄に雰囲気が出て体温が上がる。ギクシャクとした動きで足を進めたは喜多に促されるままもうひとつの布団に座るよう指示される。
布団と政宗の顔を交互に見てしまったは一瞬頭の中が真っ白になってしまい、布団の端に座り込んでしまった。
の残念な挙動に一瞬呆れたような噴出すのを我慢してるようなそんな顔をした喜多はすぐさまその顔をしまい、「それでは、ごゆっくり」とだけ残し部屋を去ってしまった。
「ぶはっ」
「んな!」
喜多の気配がなくなりしん、と静まり返ったところで政宗は噴出し噛み殺すように手で口を覆い、肩を揺らして笑い出した。その行動に赤い顔のまましかめ面で睨むにやけ面の政宗が「Sorry」と謝ってきた。
「それ、謝ってませんよね」
「お前の挙動が面白かったんだから仕方ねぇだろ」
喜多が去るまで我慢してたことを褒めてほしいくらいだぜ、とのたまう独眼竜にの目はじとりと細くなったがすぐに溜息に変えて肩を落とした。まぁ、確かに変な動きをしていたのは確かだろう。
「だって仕方ないじゃないですか。こういうの初めてなんだから」
元の世界だって結婚式をしたことがなかったんだ。ずっとずっと昔に親戚の結婚式は出たかもしれないけど。友達周りはまだ結婚ってほどじゃなかったし、式とか披露宴とかしないまま結婚してる子が殆どだった、というのもある。
「俺としてはもっと派手に触れ回りたかったんだがな」
「や、やめてください」
婚儀の話をした時に「派手にパーリーしようぜ!」と打ち出された政宗の企画にはいろんな武家を呼んだ披露宴とか市中練り歩きとかあったのだ。これ以上の胃痛の種は勘弁してほしい。
「私には、この関係と私の為に作ってくださった着物で十分です」
披露宴とかみんなにお祝いしてもらうことが嫌というわけじゃないけど、小十郎と話し、なるべく地味に婚儀を済ませたかった。それに着物は手縫いだってわかってはいたもの、制作期間はわかってるようでわかってなかった。
1度しか着ないあの白無垢は1年も月日を費やしたらしい。今の身体に寸法を合わせているから恐らく2度と着ることはないだろう。そんな貴重で莫大な金額を1年も前から私にかけていたなんて知るよしもなかった。
それだけでも十分政宗や他の人達の気持ちが見て取れた。手招きする政宗に呼び寄せられるようには布団の隅から彼の布団にまで近づいた。
出会った時から好きではいたけどこんな関係になろうとは思ってもいなかった。でも政宗は1年前にはもうそういう気持ちで見ていたのかと思うと心臓が高鳴り頬が紅潮していく。
膝の上に置かれたごつごつとした手の上に重ね置けば彼のもう片方の手がの頬をなぞる。そして見詰め合い唇を重ねた。
「紅をひいたお前も Cute だぜ」
似合ってる、とリップ音つきで唇を放した政宗は嬉しそうに微笑む。その顔を見ても嬉しくなり自然と顔が綻んだ。
「But いいのか?継室じゃなく側室で。今のお前なら片倉家の子として正室入りができたんだぜ?」
「…確かに政宗さまの正室になれたらいいなって思ってました」
彼の手の上に置いた手を握られは視線を下に落とした。正室の話は小十郎達と散々話し合った。多分小十郎も鬼庭や成実達とも話し合ったと思う。
も小十郎達も本当に願っているのは政宗の正室だ。は誰にも邪魔されない場所を獲得できるし、片倉家にとっても確固たる地位が得られる機会なのだ。それを逃す方がありえない。
「政宗さまと添い遂げたいという気持ちはずっと変わっていません。でも、妙芳さまがいなくなってまだ半年も経っていないのに私がその場所に入るということはあのお方から"奪う"ことに感じてしまって…」
今の世は戦国時代。自分も自分が愛した人も誰がいつ命を落とすかわからない。だからこそこういった儀式は正攻法だろうと、たとえ手汚いと罵られようと自分が願うことを選んでいくことが大切だと想う。
でもこれは悩みに悩んだけどこれしか選べなかった。
「私は妙芳さまのことを噂程度しか知っていません。ですが、私よりも幼い年齢で政宗さまに嫁ぎ、10年余りも伊達家とご自分のお家を守ってきたことは知っております。そして耐え難い病に心を痛めていたことも。
そんなお方の地位を私が易々といただくには時期尚早、と思いました」
妙芳さまのお家からしてみれば成り上がりもいいところだろう。だからずっと命を狙われていた。むしろ今度こそを暗殺しにくるかもしれない。聞こえる陰口では「身分不相応」と堂々と言い切られたくらいだ。そんなこと自身よくわかってるつもりだけど。
「俺が引かねぇから小十郎と頭つき合わせて出した妥協案ってところか」
「…はい」
「まったく、このkittyは」
小十郎には「お前の好きな方を選べばいい」といわれたから継室か側室か散々悩んで自分で選んだ答えだけど、小十郎は本当にこれで良かったのかな?今更そんな言葉が去来したところで政宗に腕を引かれ彼の胸に落ちた。
見上げればなんともいいがたい顔をした政宗がを見下ろしている。
「お前だって易々と今日を迎えられたわけじゃねぇだろうが」
「……」
「この傷も、この傷もお前が命を張った証だ」
生傷はとうに癒えて跡やみみずばりになっているけれど政宗は額や腕をなぞり、誰でも出来ることじゃねぇといって抱きしめてくる。それだけでは不意を突かれたように涙が溢れてくる。
「そんなお前だから俺は選んだんだ。You see?」
「…Yes.」
化粧をしてる手前、泣くことはできなくて必死に堪えているの背中を政宗が優しく撫でてくる。このタイミングでそんな優しくしてこないでほしい。せめて、火を消してくれないかな。
あ、でも消されたら消されたでその後を考えると頭が沸騰しそうになるんだけど。
-----------------------------
2018.09.21
英語は残念使用です。ご了承ください。
TOP //
NEXT