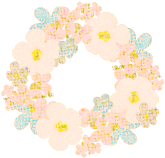生きてる証
「俺の畑を狙うたぁいい度胸だ。どこから来た?」
腕を後ろに回され、うつ伏せにさせられたは痛さのあまり唸る。男はかなり怒っていた。怖くて怖くて許しを請おうにも、口の中に土が入ってそれどころじゃない。頭を押さえつける力が半端ないのだ。
そのうち足をばたつかせる気力もなくなり、ぐうぐうと鳴る腹に反抗する気も失せたは身体の力を抜いた。
「…テメェ、腹減ってんのか?」
何日食ってねぇ?という問いに空いてる手の方で指折り数えると、身体に乗っていた重石のような身体が消えた。
「……?」
「立てるか?」
腕を引っ張られフラつきながら立ち上がるとみすぼらしい着物についた土を落とす。
が着ていたのは本当はパジャマだったがいつの間にかこんな着物を着ていた。しかも素足はこの数日間でかなり傷と土で汚れていて痛みすらよくわからない。掴まれていた腕を解すように撫でた手も傷だらけだった。
目の前の男は大人だろうか。大きな背中だ。まるで小さな子供が大人を見上げるくらいの距離を感じる。
一体自分はどうしてしまったんだろう、と先に歩く男の後についていくと彼は木の根元に置いてあった荷物から竹の筒を取り出し寄越してきた。
「飲め。水だ」
水と聞いては、栓を外すのも煩わしいと思いながら喉に流し込む。冷たい水が食道を通る感覚が心地いい。ゴクゴクと飲んでいると男がこれも食えとおにぎりを出してきた。
「……?」
「俺の飯だ。毒は入ってねぇよ」
おにぎりと男を見比べていると男は小さく笑って早く食えと促す。はペコリと頭を下げおにぎりを手に取り食べた。仄かに感じる甘味と懐かしい食感が口一杯に広がる。
「急いで食うと喉に詰まるぞ」といわれ、慌てて水を飲むと男がまた笑った。
降り注ぐ暖かい光と美味しい米と水にやっと生きてる感覚が戻ってきての目から温かい水が零れ落ちる。
「お、おいっ…」
慌てる男の横ではおにぎりと竹筒を持ちながら声をあげて泣いた。
私、生きてるんだ。
-----------------------------
2011.04.21
BACK //
TOP //
NEXT